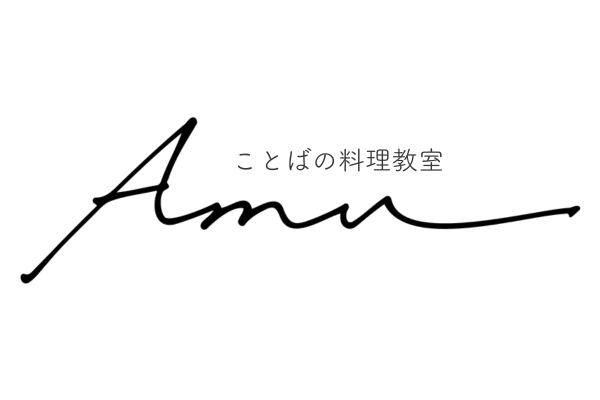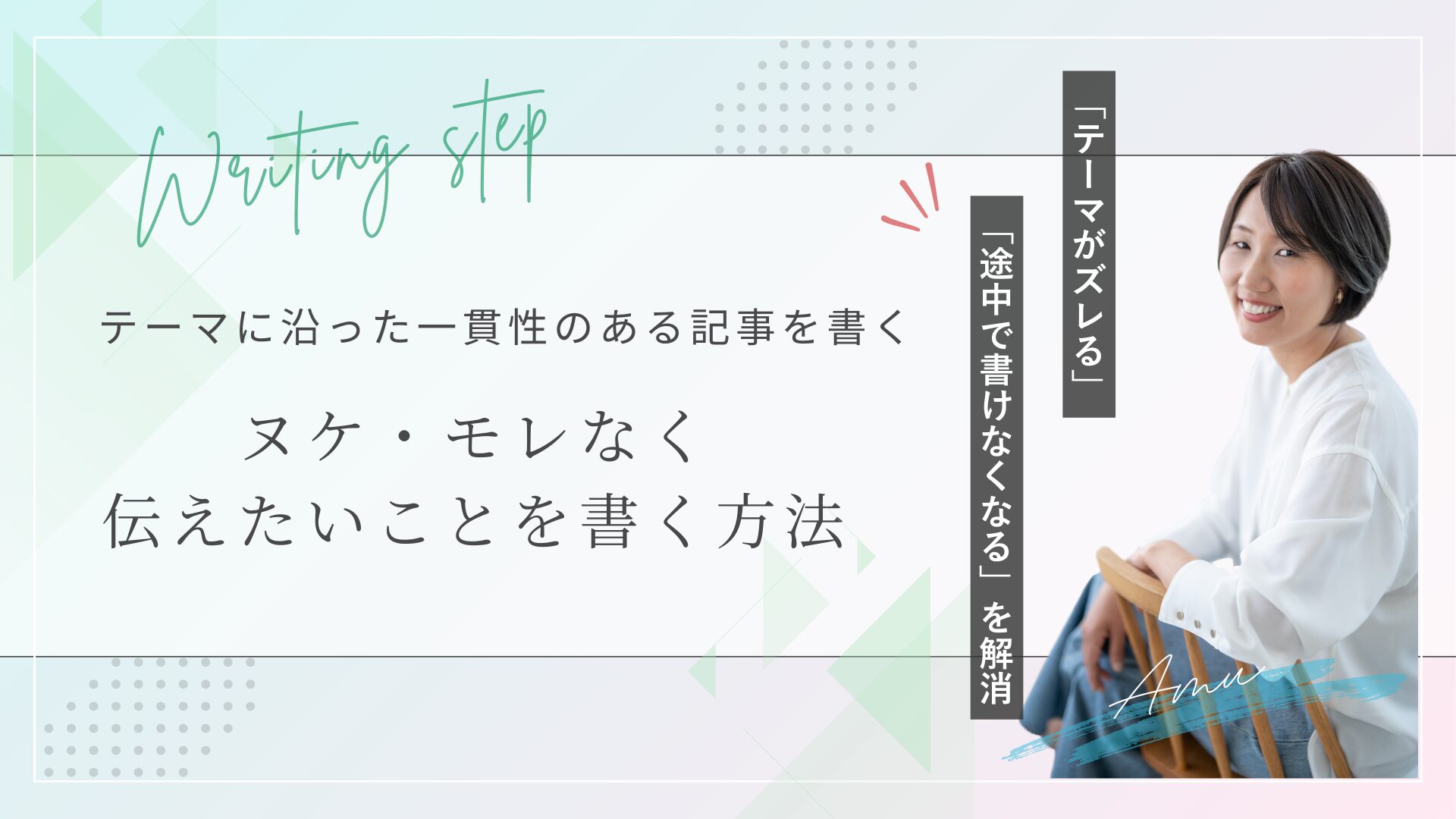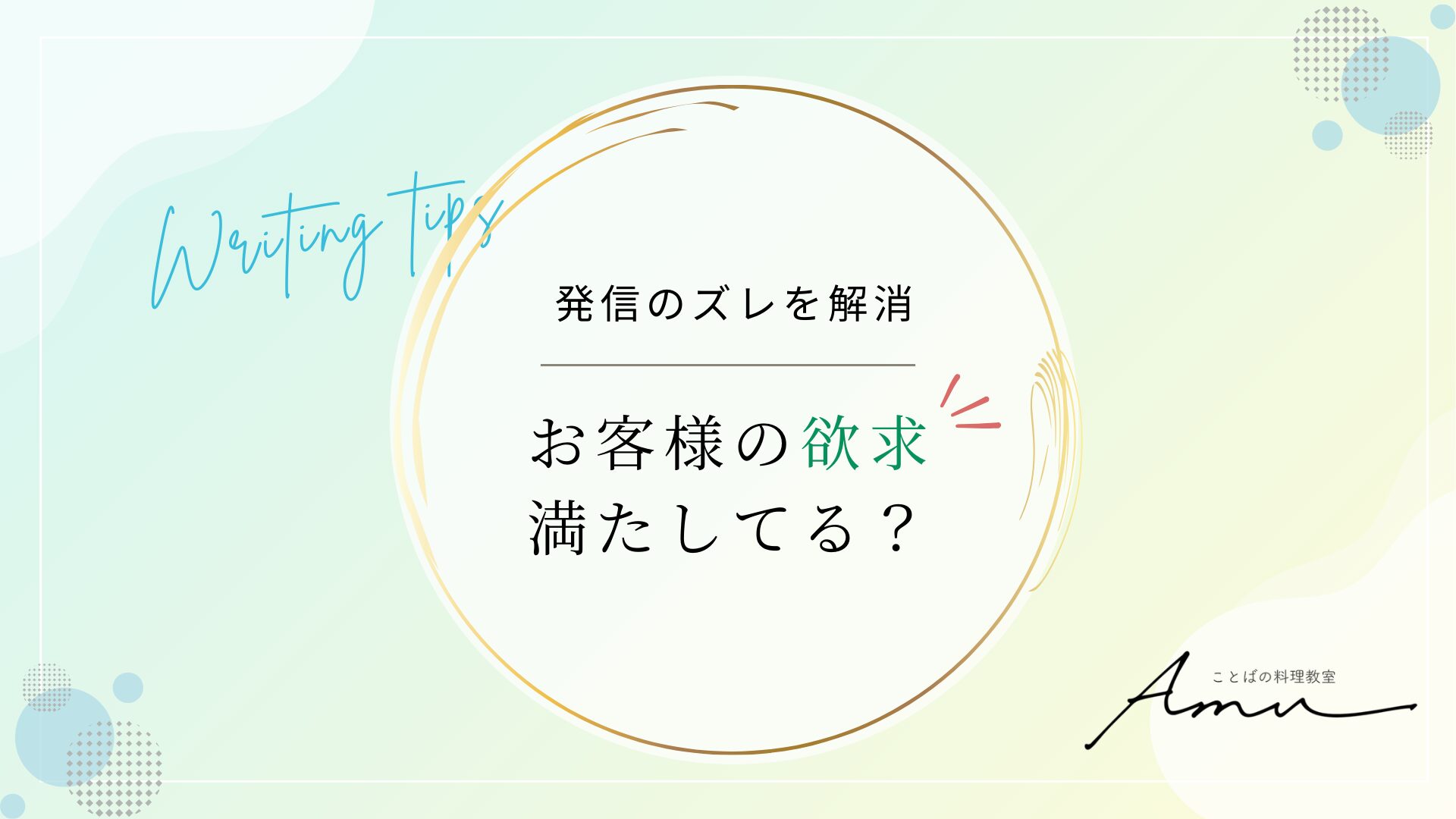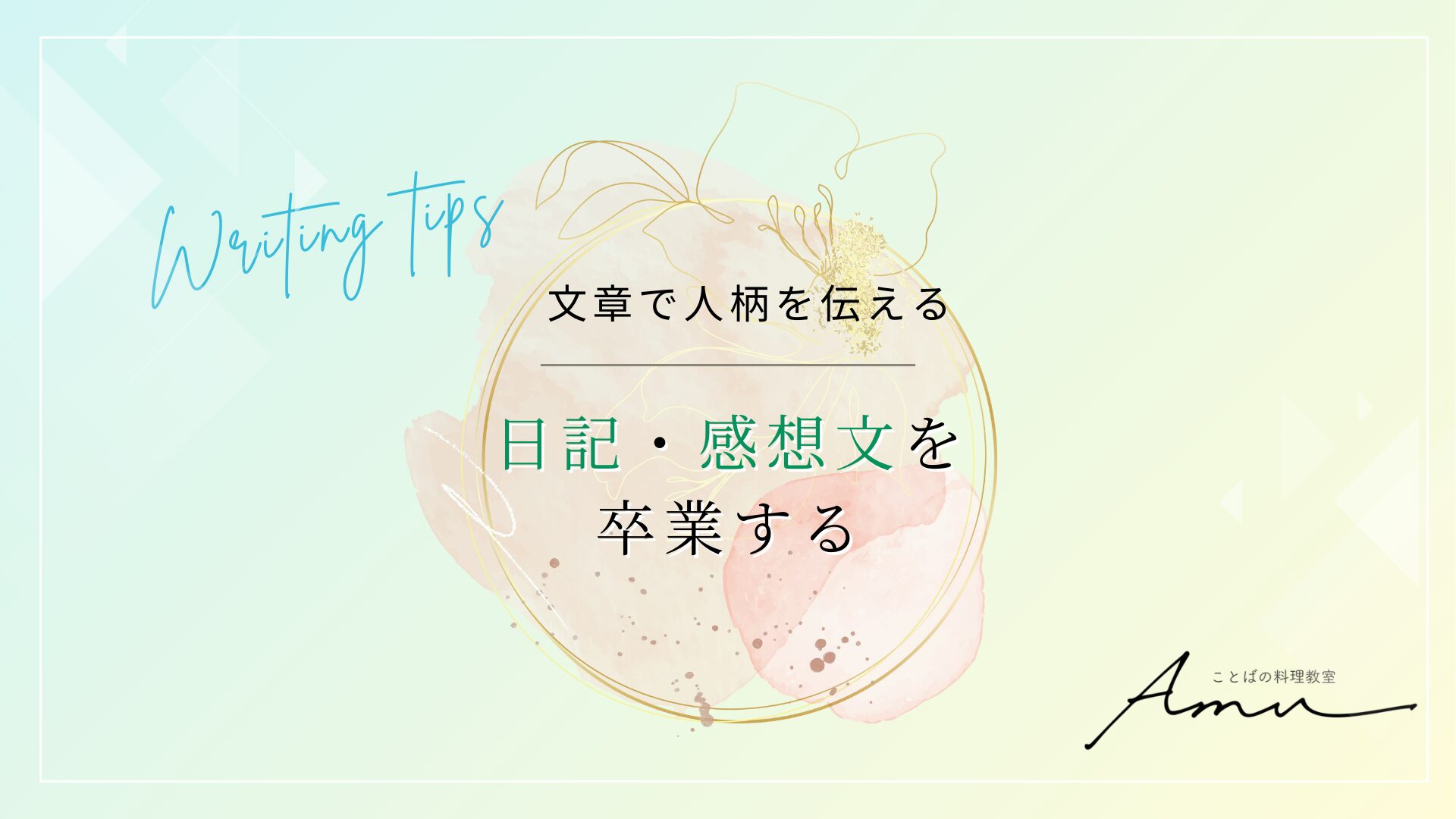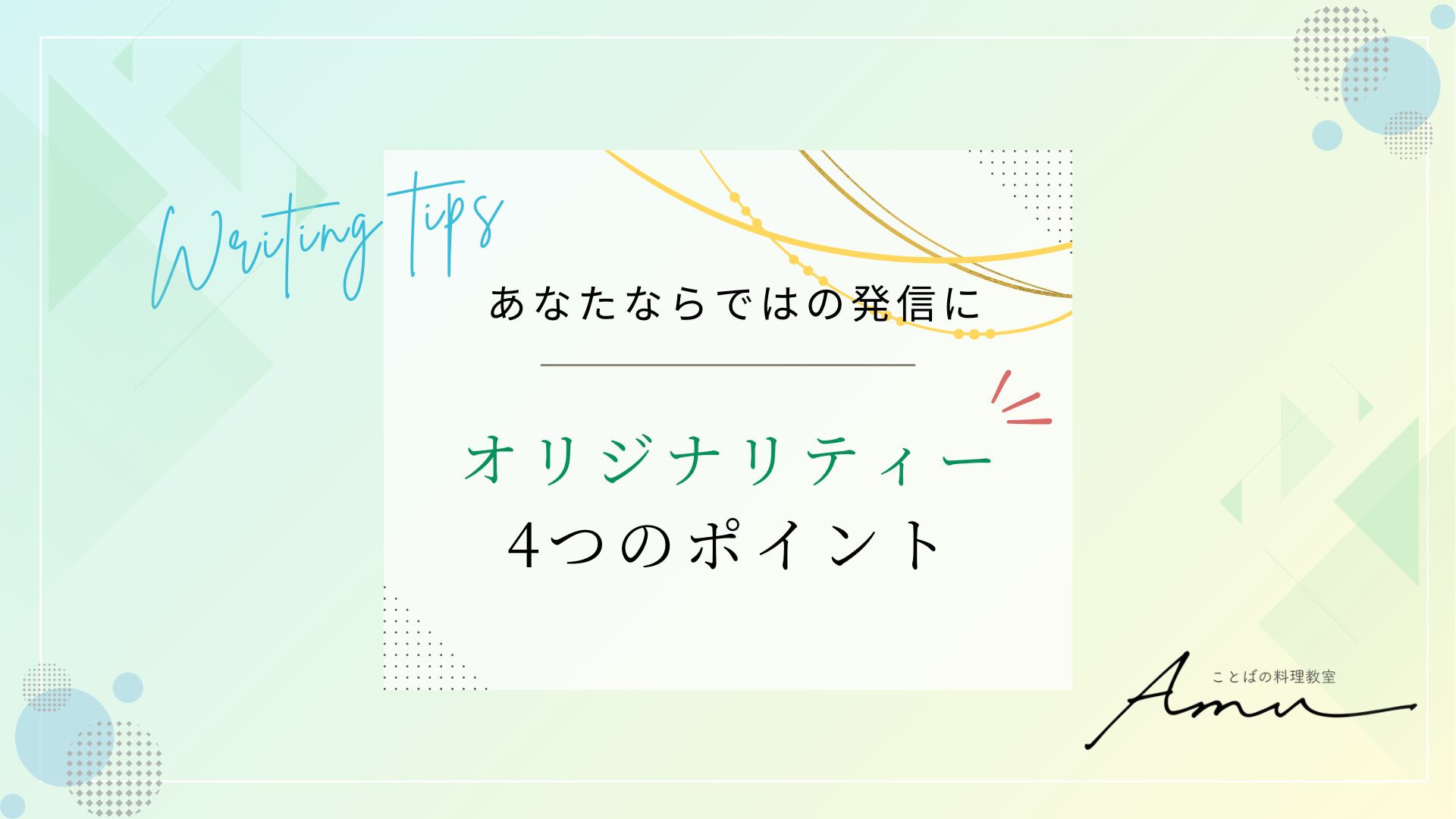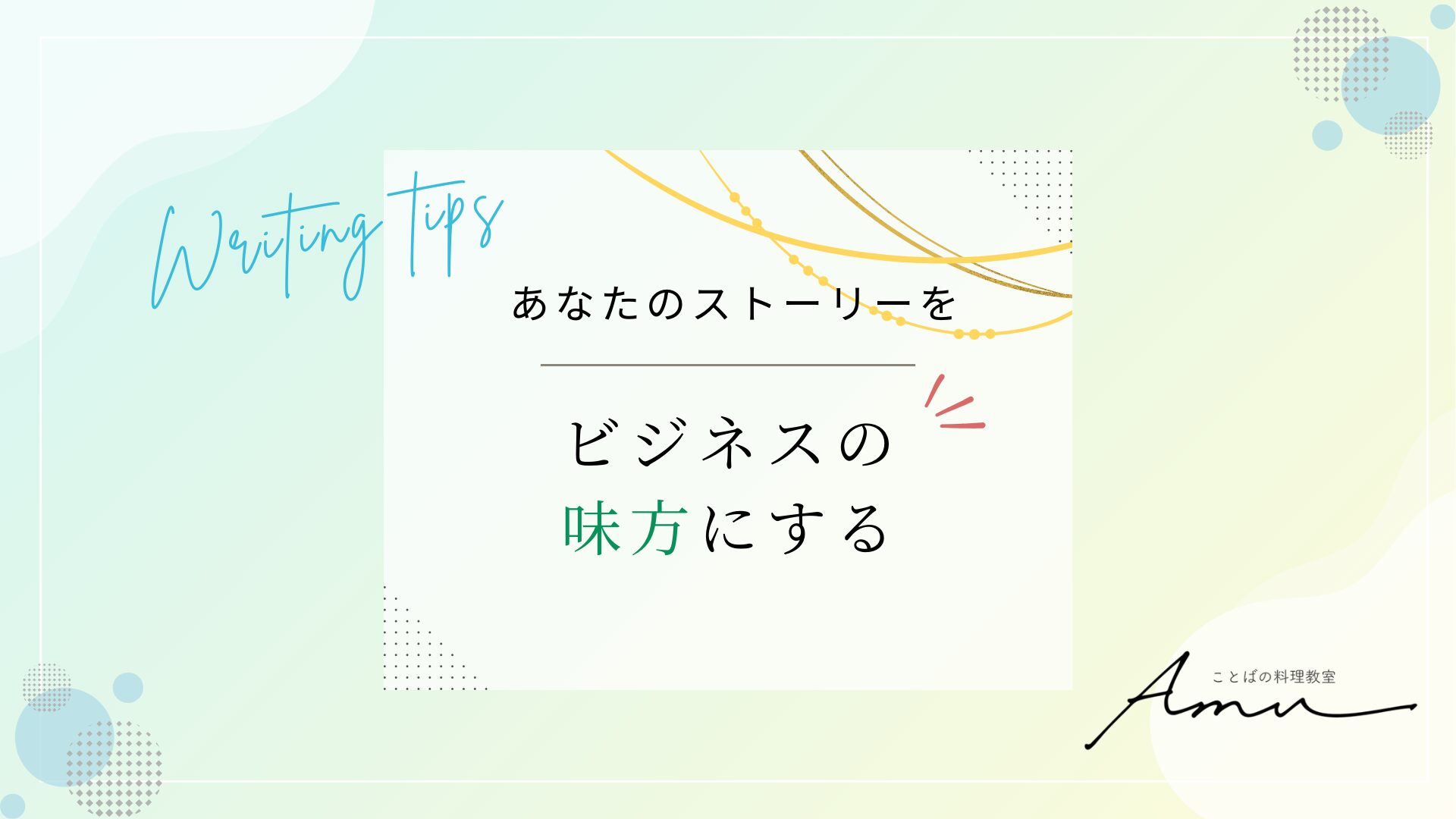【文章力アップ】語彙力がなくても書ける 伝わるブログ執筆のポイント2選
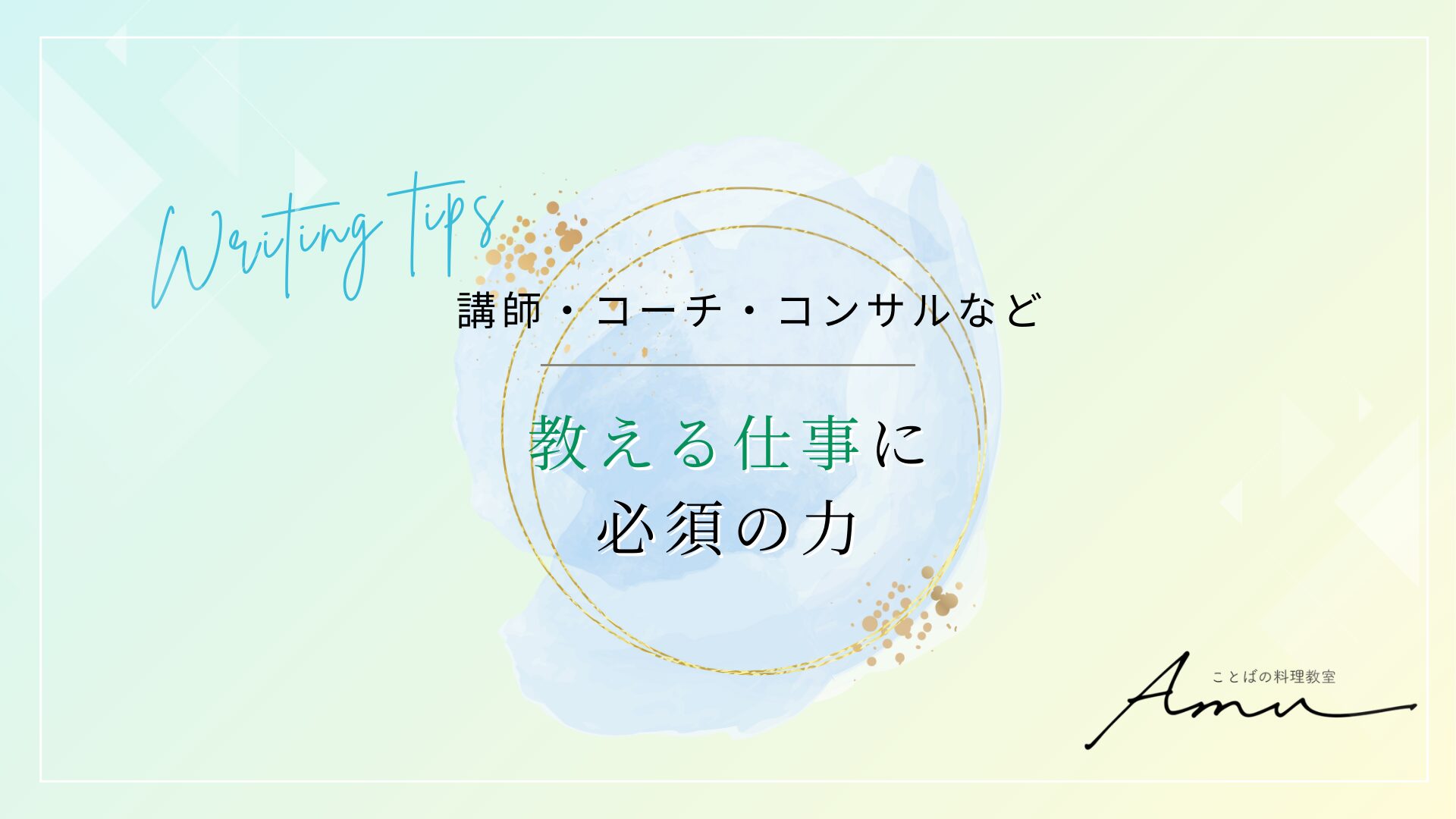

ブログでお客様の役に立つ情報を発信したいけど、うまく伝えられる気がしない…

語彙力の本でも買おうかな…

ちょっと待って~。 伝わる文章を書くために、いま以上の語彙力は必要ないよ

ライター歴10年で実感した伝わる文章のポイントを2つ紹介するね
「語彙力がある」と「伝わる」は違う
語彙力がある人って、どんなイメージですか?
(1)プロっぽい専門的な言葉がスラスラ出てくる人
(2)物知りで、他の人があまり使わない特別な言葉をたくさん知っている人
「語彙力がない」と悩む方の話を詳しく聞いてみると、たいていはこのどちらか、もしくは両方のイメージを持っていることが多いです。
でも実は、語彙力があるからといって、伝わる文章が書けるとは限りません。
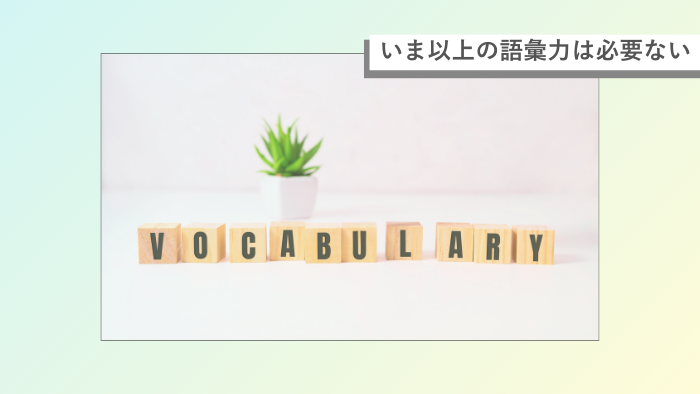
プロっぽい専門的な言葉を使わなくても、特別な言葉を知らなくても、伝わる文章は書けます。
伝えることを目的とするならば、むしろ避けたほうがいいくらいです。
伝わる文章を書くポイントは、次の2つです。
(1)読んでほしい人に合わせて言葉を選ぶ
(2)普段使いの言葉を組み合わせる
理由を例文付きで解説しますね。
【例文】専門的な言葉がNGな理由
プロっぽさ VS 読み手ファースト
たとえばオンライン起業について学び始めたばかりの人に、LPとは何なのかを説明する場合。
専門的な言葉を使ったプロっぽい文章で書くと、次のようになります。
リスティング広告やSNS広告などから遷移した訪問者が、最初にアクセスする縦長のWebページ。コンバージョンの獲得に特化している。
一方、読み手に合わせて言葉を選んだ場合は、次のような書き方になります。
サービスの特徴や良さ、購入後のメリットなどを詳しく伝えるWebページ。サービス購入などのアクションを起こしてもらうために制作する。
「LPって何?」と思っている人にとっては、(2)のほうがわかりやすいはず。
なぜならオンライン起業について学びはじめたばかりの人は、おそらくマーケティング初心者。
であれば、リスティング広告やコンバージョンという言葉を聞いてもピンとこないはずです。
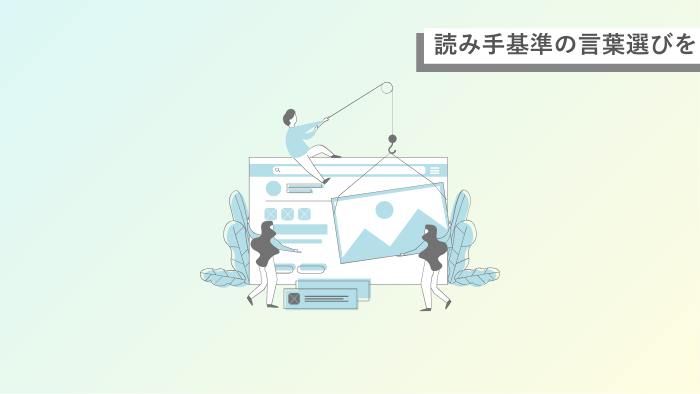
すでにLPを制作して商品を販売している人なら、(1)の専門的な文章でも理解できます。
けれどLPを知らない人にとっては、書かれてある言葉が難しい。だからLPが何なのかもイメージしづらい文章です。
知識量と経験値の差を意識する
誰かの悩みを解決する発信の場合、読み手には自分と同じ「知識量」や「経験値」がありません。
プロと同等の知識や経験があるなら悩まないので、その発信を見る必要もないですよね。
専門的なプロっぽい文章は、自分と同じ知識量や経験値がないと、相手に伝わりません。
だから伝えるときには、知識量や経験値の差を考慮して、相手が理解できる言葉で伝える必要があります。
頭の中に「?」が浮かぶと、読まれない
子どもの頃、一度は経験がありませんか?
知らない単語を調べるために辞書を引いたら、解説文にも知らない言葉が出てきて大混乱!
ググると逆に謎が深まりエンドレスネットサーフィンってこともよくありますよね

これと同じことをブログ発信ですると、読み手は「この人、知識はあるんだろうけどわかりづらい」と感じます。
一度そう感じると、「この人の発信を今後もチェックしよう!」とはなりませんよね。
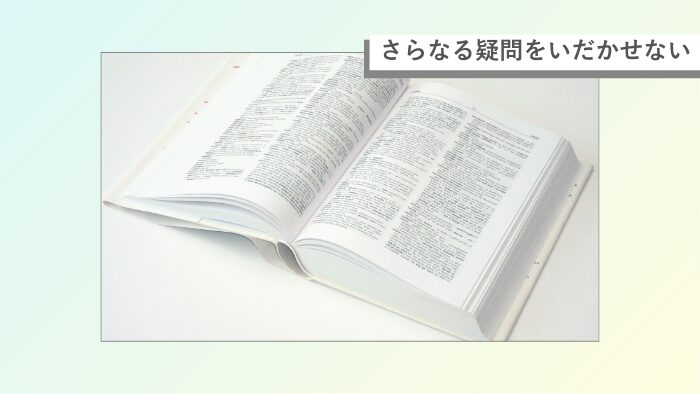
読み手の頭の中に「?」が浮かぶと、どんなに専門性があっても語彙が豊富でも、相手には伝わりません。
必要なのは、語彙力ではなく、相手の知識量や経験値に合わせて言葉を選ぶ力なんです。
【例文】特別な言葉がNGな理由
語彙力の本に載っていた「外連味」
つづいては、他の人があまり使わない特別な言葉はNG、というお話です。
先日、近所の書店に行くと、ビジネス書コーナーに「語彙力を身につけるための本」が並んでいました。
その中の1冊を手に取り、ページをめくってみたところ…
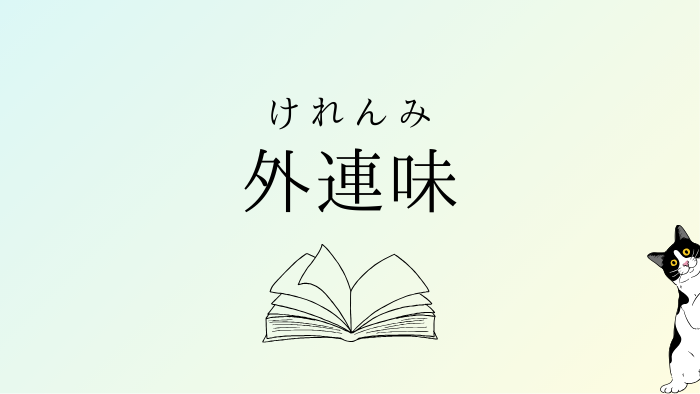
という言葉が載っていました。
恥ずかしながら私は、この言葉を生まれてはじめて知りました。私の日常には存在しない言葉だったんですね、外連味(けれんみ)は。
みなさんは、この言葉を知っていましたか?
私に学がないだけかも…という不安はありますが、日常会話で使う機会はほとんどないはず。
この言葉を使って文章をつくると、次のようになります。
外連味のあるブログタイトルは人を引き付ける半面、読み手をがっかりさせる危険性があります。
読んでいる最中に、
外連味ってどういう意味だい?

と、なりませんか?
あるいは、文脈から意味を予測して読むのではないでしょうか。
読み手は読後にスッキリしたい
こうした状態は、読み手に負担がかかります。
1つくらいなら我慢できても、何度も聞きなれない言葉が出てくると、人は読むことも理解することも諦めます。
悩みをスッキリさせるために読んでいるのに、頭が混乱してしまっては本末転倒だからです。

普段使いの言葉はストレスフリー
ちなみに外連味は、「ハッタリやごまかしを効かせた演出のこと」を指すそう。
でも、わざわざ外連味という単語を使わなくても文章はつくれます。たとえば、こんなふうに。
ハッタリのきいたブログタイトルは、人を引き付ける半面、読み手をがっかりさせる危険性があります。
外連味のある
▼
ハッタリのきいた
ハッタリという普段使いの言葉(誰が聞いてもわかる一般的な言葉)に言い換えただけで、文章の意味が頭の中にスッと入ってくるはず。
語彙をいま以上に増やす必要はない
語彙が豊富だと、物知りな印象にはなりますが、それよりも大事なのは読み手がすんなり理解できることです。
だから日常会話に困っていないのであれば、いま以上に語彙を増やす必要はありません。
普段使いの言葉を組み合わせれば、読むスピードと同じ速さで内容を理解できるストレスフリーな文章になります。
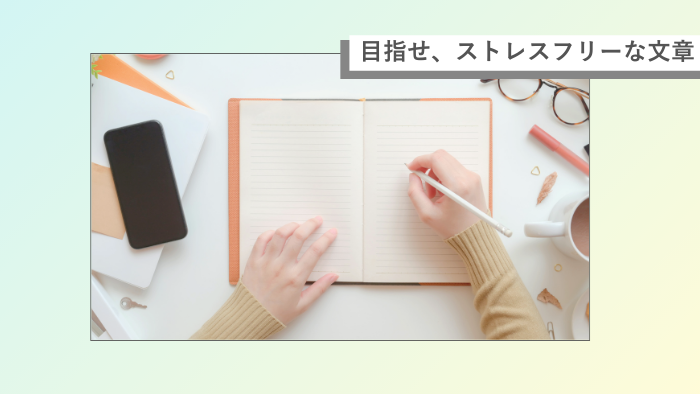
伝える力は、教える仕事の必需品
社会人になったばかりの頃、私は先輩や上司が何を言っているのかよく理解できませんでした。
「業界特有の言葉」や「会社独自の言葉」が飛び交っていたから

でも、新人教育がうまい先輩は、私でもわかる言葉に翻訳して、仕事を教えてくれました。
すると、「この先輩から教わりたい」という気持ちになるんですよね。
わかりやすさが、頼れる安心感を生む
こうした経験をふまえると、
(1)読んでほしい人に合わせて言葉を選ぶ
(2)普段使いの言葉を組み合わせる
この2つは、講師・コンサルなど、教える仕事をしている人には必須の力だといえます。

この伝え方で、
お客様がすんなり理解できるかな?
ブログを書くときには、この問いかけをしながら書いてみてください。
わかりやすく伝える力があると、誰かの「頼れる存在」になれますよ。

伝わるブログを書くサービスはコチラ